長野県 上田市・北国街道の起源と概要
北国街道は、江戸時代初期に五街道が整備される中で、北陸地方から江戸に至る経済的・軍事的なルートとして開発されました。現在の長野県上田市北部を含む信州地域は、この街道の中間地点として栄えました。特に、上田市は千曲川や善光寺平に面しており、地理的に交通の要衝でした。
北国街道の役割
北国街道は、単に物資や人の往来だけでなく、文化や情報を結ぶ大切なルートでした。
北陸の海産物や絹織物が運ばれ、信州の農産物や工芸品と交換される経済活動が活発でした。
今回訪れた、小岩井紬工房の周辺には、山際まで武者返しのように反り立った石垣や、蚕室、蔵造りの大きな家並を見ることができます。


蚕糸業の発展と北国街道
上田地域は、江戸時代から明治時代にかけて蚕糸業の中心地として発展しました。この地域の気候や地形が桑の栽培に適しており、質の高い繭が生産されました。
北国街道との関係
北国街道は物流の重要なルートだったため、上田で生産された繭や生糸が街道を通じて北陸地方や江戸に運ばれました。また、街道沿いの宿場町では、蚕種商や糸商人が行き交い、上田の蚕糸業を支えました。
明治時代になると、長野県全体が蚕糸業で日本一の生産量を誇るようになり、上田もその主要拠点の一つとなりました。この時期には、生糸は日本最大の輸出品となり、世界市場で高い評価を受けていました。




上田紬の誕生と北国街道による普及
上田紬は、蚕糸業から生まれた絹織物で、上田地域の文化と暮らしに深く根付いています。
上田紬の歴史は400年以上前にさかのぼります。江戸時代には、農家が冬の副業として糸を紡ぎ、それを織物にして生活の糧としました。これが上田紬の原型とされています。
上田紬は、北国街道を通じて他地域にも広まりました。その素朴で丈夫な品質は、農民や庶民の日常着として人気を集めました。また、上田紬を扱う商人が街道を往来し、販路を拡大していきました。
上田紬は、格子や縞模様を基調としたシンプルなデザインが特徴です。その丈夫さと温かみのある風合いは、現在も多くの人に愛されています。
伝統工芸「上田紬」の魅力を体験
上田の蚕糸業から生まれた伝統的工芸品が、400年以上の歴史を誇る上田紬です。シンプルで素朴な縞模様と、丈夫で温かみのある風合いが特徴のこの織物は、上田地域の人々の暮らしを支えてきました。現在では、工房で職人の技を見学したり、自分で織物体験をすることも可能です。伝統と技術が織りなす美しさを、ぜひ手に取って感じてみてください。
歴史と文化が交差する上田市では、日常を離れた特別な時間を過ごすことができます。古き良き日本の魅力に触れながら、伝統工芸や地域の暮らしに親しむ旅をお楽しみください。
ぜひ、上田市で歴史と伝統の魅力を発見する旅へ出かけてみませんか?






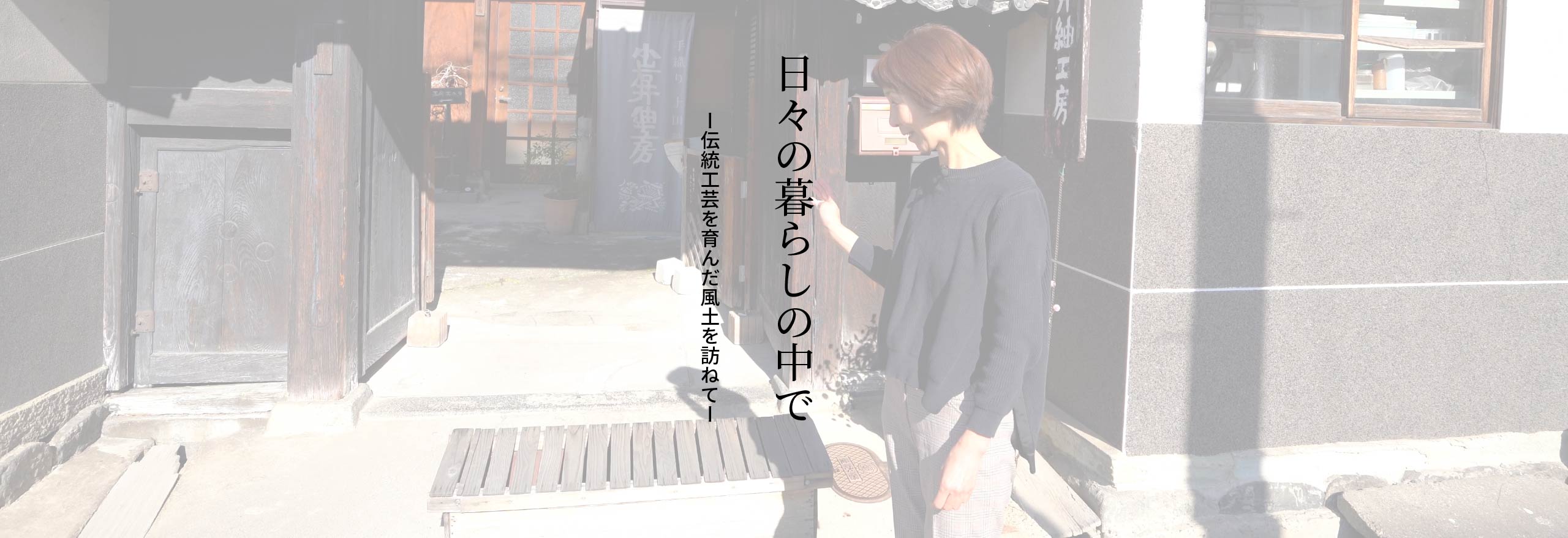
「蚕都上田」の記憶
みなさんこんにちは。 長野県上田市で上田紬を製作しています、小岩井カリナです。
私の故郷上田市は、かつては養蚕や蚕種製造業で栄えた歴史ある地域です。 今でも北国街道沿いにはその繁栄を思わせる蚕室造りの建物がたくさん残っており、この街道沿いの工房で美しい信州の四季を感じながら美しい上田紬の製作に向き合えることに喜びを感じています。
子どもの頃、毎日のように走り回った山も、湧き水が溢れる沢も、迷路のように探検した小路も、全てが今の作品につながる大切な記憶であり、故郷の景色は私の製作の力になっています。
この土地の歴史ある記憶を上田紬にのせて、これからも作品づくりに励んでいきたいと思います。
是非「蚕都上田」に遊びにいらしてくださいね。
小岩井カリナ|信州紬 手織り上田紬/長野県